


2025年4月に施行される「改正貨物自動車運送事業法」は、物流業界全体の取引慣行や安全管理体制を大きく見直す重要な転機となります。
特に軽貨物ドライバーや小規模事業者にとっても影響は小さくなく、契約や運行管理の在り方を今一度見直す必要があります。
本記事では、法改正の概要から実務的な影響、軽バンを活用するドライバーが気を付けるべきポイントまで、わかりやすく解説します。
改正貨物自動車運送事業法とは

2025年4月に施行される「改正貨物自動車運送事業法」は、日本の物流業界において大きな転換点となる法改正です。
正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」で、流通と物流の両面から業界全体の見直しを図ることを目的としています。
改正の背景には、ドライバー不足や長時間労働、物流の非効率性といった構造的な課題があります。
特に「2024年問題」と呼ばれる働き方改革関連の制限により、物流キャパシティの減少が懸念されるなか、法的な支援とルール整備が強く求められてきました。
これにより、サプライチェーン全体の効率性と安全性を向上させる狙いがあります。
改正の影響をわかりやすく解説
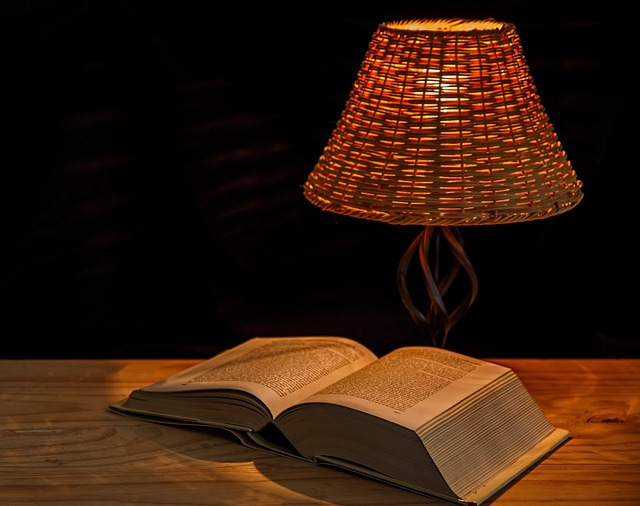
これまで、運送契約は口頭や簡易な合意で行われることも多く、契約内容の不透明さがトラブルの原因となっていました。
今回の改正では、契約時に「役務の内容・報酬の内訳(附帯業務費・サーチャージ含む)」を明記した書面を交付することが義務付けられます。
これは軽貨物ドライバーにとっても重要なポイントであり、「何を運ぶか」「どこまで運ぶか」「いくら支払われるか」が明確になることで、不当な業務押し付けや未払いを防ぐ効果が期待されます。
改正法では、元請事業者に対して「下請事業者の利益を不当に損なわないこと」が義務化されました。
これは法文上、第24条第2項に位置づけられ、いわゆる「健全化措置」として明記されています。
軽貨物運送のような下請構造が多い業態においては、このルールが元請による適切な管理体制の整備と透明な取引関係の構築につながると期待されています。
1.5トン以上の貨物を請け負い、下請けに再委託する場合、元請は「実運送体制管理簿」を作成・1年間保存しなければなりません。
管理簿には、下請事業者の情報、貨物の内容、運送経路、委託階層などを記録します。
この義務化により、長すぎる下請け構造や、実態の不透明な再委託を抑止することが目的です。
これまで規制が緩やかだった軽トラック事業者にも、今回の法改正で新たな義務が課せられます。特に以下の2点が重要です。
軽貨物運送でも、安全管理の知識や契約管理が重要視され、一定の教育が必要になります。
国土交通大臣に対する事故報告の義務が課され、違反時の行政処分内容が公表される仕組みに。
これは小規模事業者にとっても大きなリスク要因となります。
改正の影響に対し軽貨物ドライバーが気を付けること
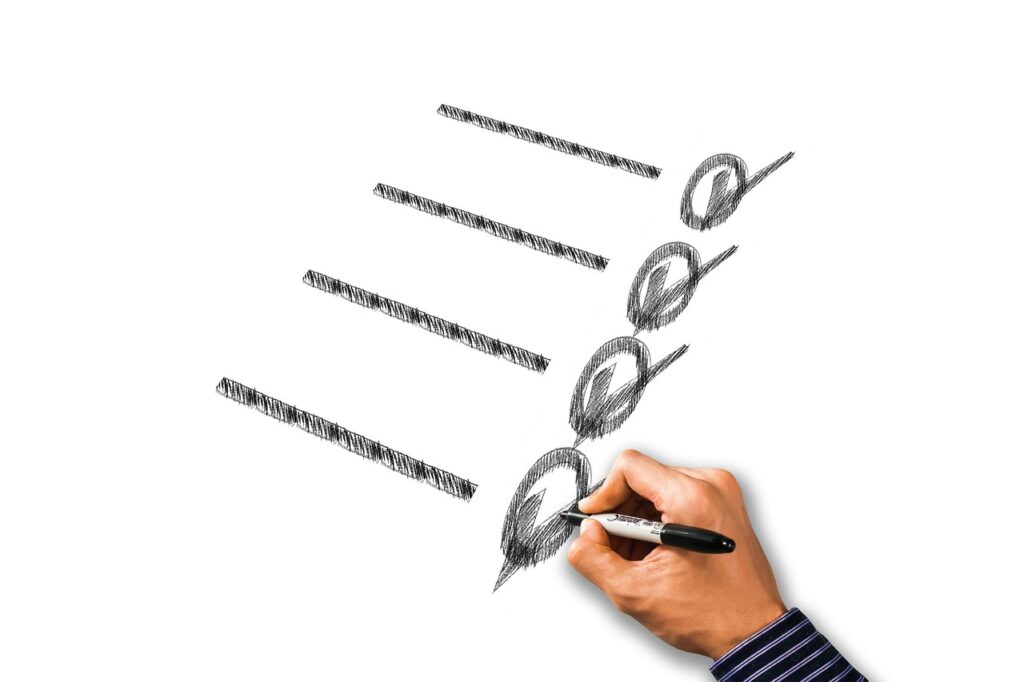
2025年の法改正により、軽貨物ドライバーにも具体的な責任と義務が生じることになります。
ここでは、改正法施行に向けて軽貨物ドライバーが気を付けるべきポイントをわかりやすく解説します。
法改正により、運送契約時に「役務内容」と「報酬」の詳細を明記した書面の交付が義務化されました。
これはドライバーにとっても大きなメリットであり、自分がどのような業務を担い、どれだけの報酬を受け取るのかを事前に把握できます。
万が一、契約内容が曖昧なまま業務を始めると、報酬未払いなどのリスクが生じるため、契約書は必ず確認・保存する習慣をつけましょう。
軽貨物事業者であっても、事故報告の義務や安全管理体制の整備が求められるようになります。
特に、交通事故が発生した場合は、速やかに国土交通省への報告が必要となり、違反があれば事業者名が公表される場合もあります。
また、元請や委託元からの要請で「点呼」「運行記録」の提出を求められるケースも増えることが予想されます。
運転日報や業務内容を記録するアプリの活用なども視野に入れ、日頃からの記録・報告体制を整えておくと安心です。
法改正により、軽貨物のドライバーにも「管理者の選任」や「講習受講」の義務が広がる可能性があります。
これは安全対策の一環であり、法令に基づいた運送業務を行うための知識を習得することが求められます。
講習は、オンラインや自治体・業界団体が主催するものがあり、参加によってトラブル防止や信頼獲得にもつながります。
自己流の働き方から一歩進み、専門職としてのスキルアップを図ることが重要です。
物流の現場では、委託・再委託が複数段階にわたることが多くあります。今回の改正では、「実運送体制管理簿」の作成と保存が義務付けられ、自分がどの段階で業務に関わっているかが記録されます。
これにより、責任の所在や契約条件の不明瞭さが減少しますが、同時にドライバー側も「自分がどの事業者の下請として業務を行っているのか」「再委託は法的に適正なのか」を把握しておく必要があります。
改正貨物自動車運送事業法の影響についてよくある質問

A. はい、大いに関係します。
「軽貨物だから関係ない」と思われがちですが、今回の法改正では軽トラック事業者に対しても契約管理、安全運行、報告義務などが適用される場面が出てきます。
特に、軽貨物配送の多くは下請構造の中にあり、元請・委託元の体制変化が直接ドライバーに影響するため、業務内容の把握と法令対応が求められるのです。
A. はい、場合によっては元請が「実運送体制管理簿」に記録する義務があります。
1.5トン以上の貨物を扱う案件などでは、委託元が自社で再委託先を記録する必要があります。
その対象としてドライバーや軽貨物事業者の情報も含まれる場合があります。
自分がどのような契約構造の中にいるのか、元請や下請のどの位置にいるかを把握しておくことは、万が一のトラブルや責任問題に備えるうえでも有効です。
A. 書面交付義務違反、届出違反、安全義務違反には罰則があります。
たとえば、運送利用管理規程を提出しない元請には100万円以下の罰金が科される場合もあります。
軽貨物事業者に対しても、事故報告を怠ると行政処分や事業名の公表対象になる可能性があります。
まとめ
2025年の「改正貨物自動車運送事業法」は、単なる法的変更ではなく、物流業界全体が「透明性」「効率性」「安全性」を重視した運営にシフトしていく大きな転機です。
軽貨物ドライバーや個人事業者にとっても、これまで以上に契約内容の確認、安全運転の徹底、法令理解が求められる時代になったといえるでしょう。
こうした変化の中で、軽バンリースの活用は、法改正への実務的な対応策として非常に有効です。
リース契約なら、定期的な点検整備や事故対応の体制も整っており、安全管理義務の履行もしやすくなります。
また、契約内容の明確化や業務範囲の確認にもつながり、法令に則った安心の運用が可能です。
配送用の軽バンのレンタルやリースを検討されている方は、軽バンリース・レンタル本舗へお問い合わせください。
自社認定整備会社で整備・メンテナンスを行っておりますので、安心・安全にご利用が可能です。