


近年の宅配業界は、インターネットショッピングやサブスクリプションサービスの普及に伴い、急速に成長を遂げています。
しかし、この成長の裏では、労働環境の悪化や交通事故の増加など、多くの課題が指摘されています。
このような状況に対応するため、2025年4月から「貨物軽自動車安全管理者」の選任や講習受講が義務付けられる新制度が導入されます。
本記事では、貨物軽自動車安全管理者の役割や制度の概要、事業者が今後気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。
宅配業界における貨物軽自動車安全管理者とは

貨物軽自動車安全管理者とは、事業者が保有する軽貨物車両の安全運行を確保するために選任される責任者です。
宅配事業においては、交通事故を未然に防ぎ、効率的で安全な運行を実現するために欠かせない存在となっています。
貨物軽自動車安全管理者には、以下のような重要な業務が求められます。
ドライバーの健康状態を管理することは、安全な運行の第一歩です。アルコールチェックや疲労の確認を行い、過労運転を防ぐ取り組みが必要です。
また、定期健康診断の手配や、必要に応じたストレスチェックも実施します。
たとえば、過労による判断力の低下が原因で事故が発生するケースを防ぐため、ドライバーが十分な休息を取れるスケジュールを組むことも重要です。
安全管理者は、運行計画を作成し、ドライバーに適切な指示を行います。
具体的には、交通状況や天候を考慮した最適な配送ルートの設定や、配達スケジュールの調整などがあります。
運行中のリアルタイムな状況把握も求められ、GPSシステムを活用してトラックの現在地を確認することで、問題が発生した場合に迅速に対応できます。
車両管理は、軽貨物配送業界における安全性を支える柱の一つです。
安全管理者は、タイヤの空気圧、エンジンオイル、ブレーキの効きなどを定期的にチェックし、不具合が見つかった場合には整備を手配します。
また、車両ごとに点検記録を保存し、整備履歴を明確にしておくことで、車両の安全性を長期的に維持することが可能です。
ドライバーに対する安全教育の実施も、安全管理者の重要な役割です。
教育内容には交通法規の遵守、車両点検の重要性、危険運転の防止策などが含まれます。
特に、若年層や高齢ドライバーに対しては、年齢や経験に応じた特別な指導を行うことが推奨されます。
事故が発生した際には、迅速な対応が求められます。安全管理者は、事故原因の調査や被害者との調整、再発防止策の策定を行います。
また、事故報告書を作成し、必要に応じて国土交通省や保険会社に報告します。
2025年4月から施行される制度改正の概要
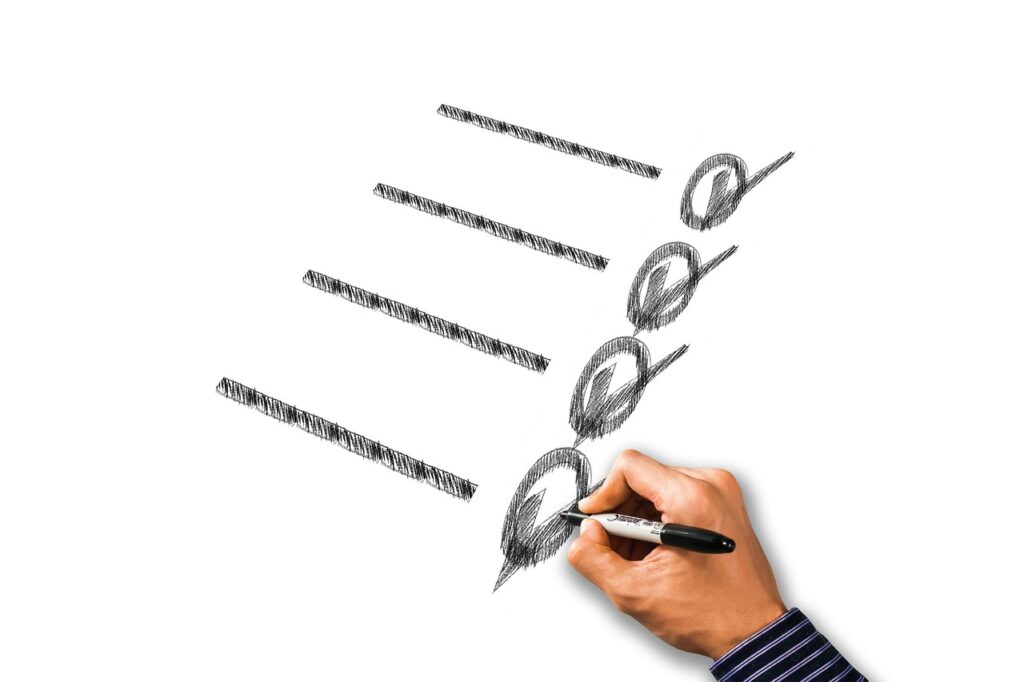
2025年4月から始まる新制度は、軽貨物運送事業者の安全管理体制を強化し、事故のリスクを最小限に抑えることを目的としています。
事業者は、事業規模に応じて安全管理者を選任し、指定の講習を受講させる義務があります。
この講習では、運行管理、交通法規、事故対応などの専門知識が提供されます。
講習を修了した安全管理者は、選任通知を国土交通省に提出する必要があります。
運行計画、点検記録、ドライバーの健康状態に関する記録を作成し、最低5年間保存することが求められます。
これにより、万が一の事故やトラブルが発生した際の迅速な対応が可能となります。
事故が発生した場合、詳細な記録を作成し保存することで、再発防止策の策定や関係機関への報告に役立てられます。
重大事故が発生した際には、速やかに国土交通大臣に報告することが義務化されます。
この報告により、業界全体の安全性向上につながる指導や支援が提供されます。
高齢ドライバーや違反歴があるドライバーに対しては、適性診断を実施し、特別な指導・監督を行う必要があります。
貨物軽自動車安全管理者の罰則規定

新制度では、義務違反に対する厳しい罰則が設定されています。
管理者を選任しなかった場合、100万円以下の罰金が科されます。
また、繰り返し違反が発生すると事業停止命令が下されることもあります。
重大事故未報告の場合には、50万円以下の過料が科されます。
重大事故の報告を怠ると、行政処分が科されるだけでなく、社会的信用を失う可能性があります。
虚偽の記録や報告が発覚した場合にも、未報告の場合と同様50万円以下の過料が科されます。
宅配を行う事業者が今後気をつけるべき点

新制度に対応するため、宅配事業者が取るべき具体的な行動を以下にまとめました。
早めの対応が、新制度への適応をスムーズに進めるための鍵です。
具体的な取り組み
運行中のリアルタイム管理は、事故防止や効率向上に直結します。
具体的な取り組み
事業全体で安全性を徹底する仕組みを作ります。
具体的な取り組み
高齢ドライバーは経験豊富な一方で、体力や判断力の低下が課題となります。
具体的な取り組み
安全運行の基盤として、車両のメンテナンスを怠らないことが重要です。
具体的な取り組み
今後の法改正や新たな規制に備えるため、情報収集を欠かさない姿勢が求められます。
具体的な取り組み
万が一事故が発生した場合の対応を事前に整備しておくことが必要です。
具体的な取り組み
まとめ
貨物軽自動車安全管理者の選任や講習受講が義務化される新制度は、宅配業界全体の安全性と信頼性を向上させるための重要な取り組みです。
この制度は、交通事故の減少やドライバーの健康維持、車両管理の徹底を目的としており、事業者にとって大きな転換点となります。
事業者は早期に対応を開始し、適切な安全管理体制を構築することが求められます。
具体的には、安全管理者の選任や講習受講を速やかに進めるとともに、運行記録の作成・保存や車両点検の徹底を行う必要があります。
また、高齢ドライバーや特定のリスクを抱える運転者に対しては、適性診断や特別な教育を実施することで、安全性をさらに高めることができます。
新制度に対応することは一時的な負担に感じられるかもしれませんが、長期的には事故リスクの低減や業務効率の向上、さらには顧客や取引先からの信頼獲得につながる重要なステップです。
宅配業界全体で安全管理を徹底し、安心・安全なサービス提供を実現するために、関係者全員で取り組んでいきましょう。
宅配を行っている事業者の方で、軽バンのレンタルやリースを検討されている方は、軽バンリース・レンタル本舗へお問い合わせください。自社認定整備会社で整備・メンテナンスを行っておりますので、安心・安全にご利用が可能です。