


形式的な安全管理では、命も信頼も守れない。
業界全体での再構築が必要であることが浮き彫りになる事件が起きました。
◆ 日本郵便(JP)全国7割以上の拠点で「点呼不適切」が発覚

2025年6月、日本郵便が保有する「ゆうパック」などの配送用車両に関して、業務前に行うべき点呼(運転者の健康状態や飲酒確認など)を、全国の拠点の約76%で適切に実施していなかったことが、国土交通省の調査により明らかになりました。
「点呼」は貨物自動車運送事業法によって義務付けられているもので、ドライバーの安全運転を担保するための最低限のルールです。
このルールを軽視・形骸化していた事実は、同社の安全管理体制全体に対する不信を招く結果となりました。
◆ 何が問題なのか?形骸化した“安全ルーチン”
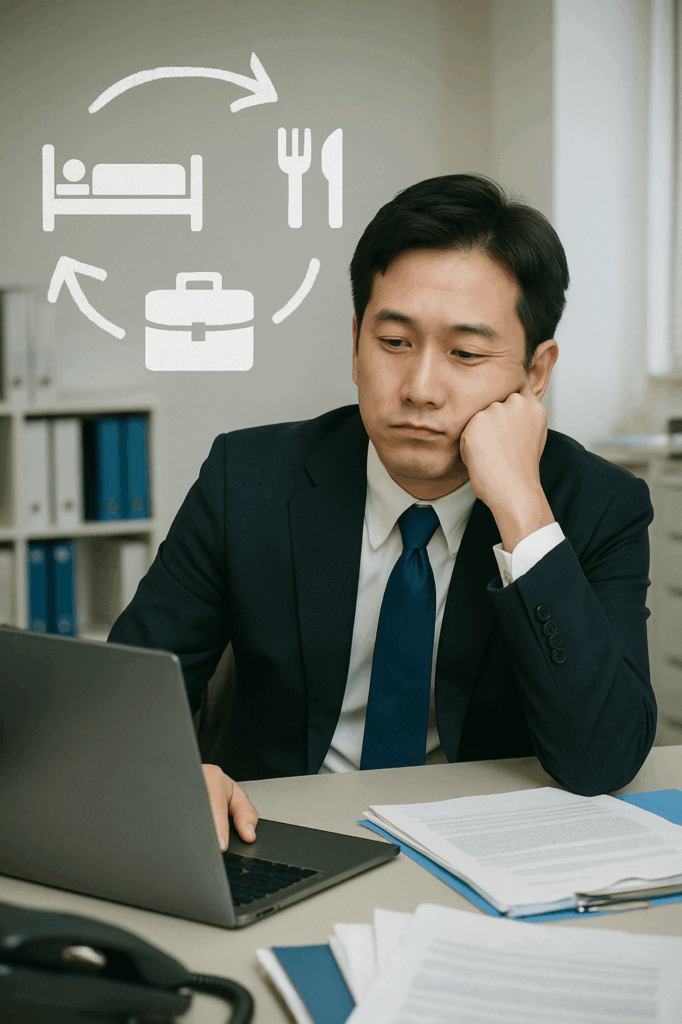
今回の件で最も深刻なのは、安全確認が単なる「チェック作業」になっていたことです。
こうした実態は、「人手不足」や「業務量の多さ」によって生じた運用上の妥協とも取れますが、本質的には組織全体が安全管理を“実績や数字のための作業”と見なしていた構造的問題にほかなりません。
◆ 物流業界への不信と波及リスク

今回の不祥事の波紋は、日本郵便という一企業にとどまりません。郵便・宅配という公共的性質を帯びた業務において、安全軽視は国民生活にも直接的な影響を及ぼすものです。
特に、地方においては日本郵便がほぼ唯一の物流手段となっている地域もあり、生活必需品の輸送に支障をきたす事態も懸念されています。
◆ 人手不足と委託依存
今回の問題の根底には、以下のような構造的課題があります。
つまり、「働き方改革」や「業務効率化」の掛け声のもと、安全確認という本来最も重要な手続きが後回しになっていたという現実です。
◆ どう立て直すのか?
日本郵便は、すでに社内調査と再発防止策の立案に着手し、以下のような対策を講じると発表しています。
● デジタル点呼システムの導入:日時・顔認証付きで実施記録を残す。
● 委託業者への安全教育徹底:契約条件に安全管理義務を明記。
● 第三者機関による監査導入:自主監査にとどまらない外部視点の確保。
● 再発防止委員会の設置:経営トップを巻き込んだ監視体制の構築。
しかしながら、これらが本質的な改革となるかどうかは、現場の理解と実行力次第です。制度を整備しても、現場で「また形だけ」になれば、同じことが繰り返されるでしょう。
◆ 問われているのは「信頼の回復力」

今回の問題は、一企業のミスとして片づけるには重すぎる社会的意味を持っています。「点呼」という一見地味な手続きこそが、組織の信頼、ドライバーの命、そして社会全体の安全を支えているのです。
日本郵便に求められるのは、「やらなきゃいけないからやる」ではなく、「守るべきものがあるからやる」という本質的な意識の転換。安全は「形式」で守れないという教訓を、業界全体で共有し、持続可能な配送インフラを再構築する契機とするべきです。